 |
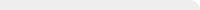
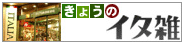

|
 |
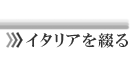 |
| 第6回 思い出あぶり出し |
トリノのポンバ通りに面したホテルの窓から顔を出すと、ちょうど真下に古いチンクエチェントが停まっていた。
くすんだ赤いボディに黒のキャンバス・トップ。そばに若い女性が立っていた。
5年ほど前まではトリノ市内で1日に何台も目にしたチンクエチェントも、最近はほんとに少なくなった。
もっとも、もう40年以上も前のクルマだから、影さえなくって当たり前、
現役で走っている姿を見かけることの方が不思議な話だ。
それでも、空冷2気筒500cc、パワーも20馬力に満たないこのクルマがここまで生き長らえたのは、
イタリア人が特別にモノモチがいいから、なんていうことではもちろんなくて、
それがある世代以上の人々にとっての、それぞれの自分史を彩る存在にほかならないからだ。
苦さも甘さも含めて、今はもうすべてノスタルジックかつセンチメンタルに「あの頃」と括ってしまえる過去のある時期、そしてそこにいた自分。
どんなに速いクルマで追いかけても過ぎ去った時間は戻ってこないけれど、過去を共に生きたクルマなら、今この時にさえ「あの頃」を呼び覚ましてくれる。
イタリアの人にとって、チンクエチェントとはそんな意味を持つクルマ、そしてそれこそがチンクエチェントなのだ。
時代の匂いとか空気とか、そういうものを確かにこのクルマは、その小さなボディのそこかしこに今も湛えている。
僕はカメラを取り出して、窓からシャッターを切った。
ファインダーを覗きながら、ちっちゃいな、と思った。
「ちっちゃい」とか、あるいはイタリア語で「ピッコロ」とか、口にしてみるとよくわかる。
そういう言葉の語感そのものなのだ、チンクエチェントって。
このちっちゃなクルマが街中に溢れていた頃の、そしてそれが人々にとってのささやかな憧れだった頃のイタリアって、どんな国だったのか。
ジジイになった僕はチンクエチェントを眺めながらそんなことを思う。
戦後の混沌から這い出そうとしゃにむに頑張っていたイタリア、抱いた希望が漆黒の夜空に置いた星のようにキラキラ輝いていたイタリア、戦後のいわば“イタリアの青春期”への言葉にならない直感的な共感が、僕の内には確かにある。
老眼が進み、視度調整機能のないコンパクトカメラのファインダーの中でぼやけるチンクエチェントの姿が、そのままモノクロームのイタリアへと繋がってゆく。
なあ〜んにもすることのない1999年の秋、日曜日の午後だった。
出発、あるいは始まり。
チンクエチェントを見ているとそんな言葉を連想する。その慎ましやかな佇まいが、最初の一歩、ということを感じさせる。
自分にとっては一体いつが出発だったのか、カメラをベッドの上に放り投げて、度の合わなくなりつつあるメガネの汚れを拭き取りながら考える。
ランニングシャツにセミ採り用の網、そんな姿で真夏の妙に白っぽい風景の中にいる少年時代の自分。
振り返ると記憶はいつもそこで止まるから、その時が僕の出発だったのかもしれない。
初恋の武田和子ちゃんのことを考えながらセミを追い、さびれた神社でバッドを振り回せば日が暮れた。なんと幸せな日々。
軋む木の床の校舎、彫刻刀で削られた机、給食費や教材費の納入日にも、そして林間学校の日にも、学校を忘れなければならなかった友。
貧しさと隣り合わせの日々。あれが出発だったと自覚すらされないささやかな出発の日をあとにして、僕はいつしかセミ採り網を捨て去り、友と離れ、今、イタリアのホテルの窓から古きチンクエチェントを眺めている。
そしてそこでは、もう何年も思い出すことさえなかったはるか昔の些細なこと、たとえばそれは友達の着ていたセーターの柄だったり、進学教室のテスト用紙のインクの匂いだったり、サイダーの風呂に入りたいと思っていた気味の悪い自分だったりするのだけれど、そんなことが脈絡もなく次から次に浮かんでくるのだった。
技術革新の速度が今よりもゆっくりしていた時代には、クルマに限らず人間とモノとの付き合いも、時間的には長く、距離もずっと近かった。
社会全体が今のように豊かではなかったから、大切に使ったというのも、人間とモノとの緊密性を支える要素だった。
そう考えてみると、チンクエチェントはつくづく幸せな時代に生まれたクルマである。
そしておそらく、こんなふうにその時代の要請を過不足なく体現し、かつそこにすっぽりはまり込むクルマは、もう二度と現れないだろう。
あ、そうそう、パンダの存在を忘れてはいけなかった。
知り合いの初老のイタリア人に言わせれば「最後のイタリアのクルマだった」フィアット・パンダである。
つまり、イタリア製で、イタリア人の等身大の生活に寄り添っていて、イタリアの心があり、イタリアのデザインをまとったクルマ、ということではパンダがアンカーだった、と彼は言ったのだ。
わかる。それは十分にわかるな。
イタリア人の誰もパンダに憧れてはいないけど、誰もがパンダをイタリアのクルマとして認めている。
トリノの地元紙『La Stampa』もこの2月に、“パンダ20周年”の記事を大きく掲載していた。曰く、20年間、400万台、31カ国。
さらに付け加えれば、イタリア国内における直近の月間販売台数でも、プントに次ぐ第2位の座を占めるクルマはパンダなのだ。
この事実は、自動車にとっての進歩とは一体何なのか、という根源的な問いを確実にそこに含んでいるし、少なくとも、クルマと人の繋がりがスペックなんかを吹き飛ばした地点で成り立っていることを教えてはくれるだろう。
そのパンダにも、もうすぐ幕が引かれる。
クルマはこれから先どこを目指していくんだろうか
。 思い出をあぶり出しのように浮き上がらせてくる自動車は心にはちょっと重いけど、その程度の重さもない人生は、ヤマンバに混ざって踊る若い男のパラパラにも似て、ちょっと哀しい。 |
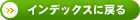
|
 |